デジタルギフトで叶える福利厚生|社員が本当に喜ぶ活用法と最新事例
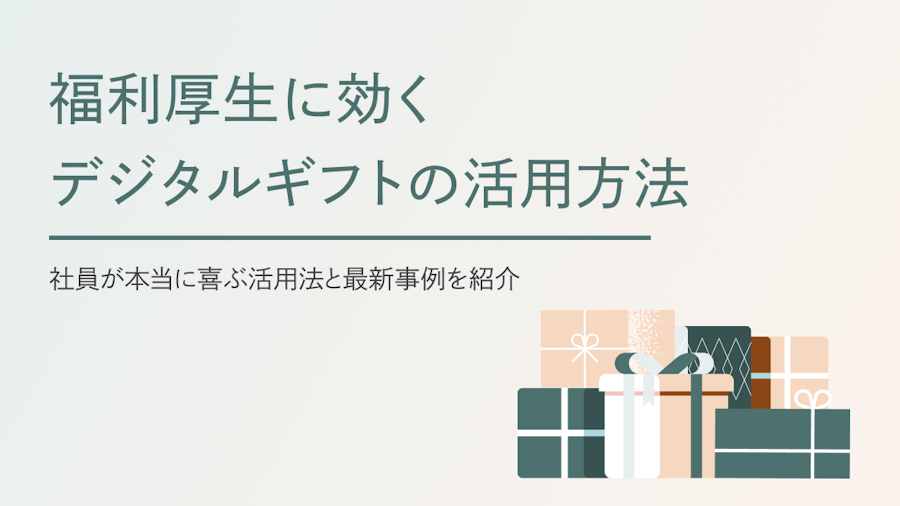
働き方の多様化が進むなか、社員に本当に喜ばれる福利厚生のあり方が見直されています。そんな中で注目されているのが、「デジタルギフト」を活用した福利厚生制度です。従業員が“欲しいもの”を自由に選べる柔軟性はもちろん、管理や配布のしやすさから人事・総務担当者にとっても導入しやすい手段として人気が高まっています。
本記事では、従業員満足度を高めるデジタルギフトの活用法や選び方、導入メリット、実際の事例までをわかりやすく解説。社員にも企業にもプラスになる、これからの福利厚生の形を一緒に考えてみましょう。
関連記事▼
社員に喜ばれる福利厚生ギフトとは?最新調査からおすすめプレゼント36選を紹介
福利厚生におすすめのデジタルギフトとは?
「デジタルギフト」とは、メールなどを通じて、相手にオンラインで贈れるギフトのこと。コンビニやカフェで使えるチケットから、百貨店やECサイトで選べるポイント型ギフトまで、種類や価格帯も多彩です。
受け取った側はスマホやパソコンから簡単にギフトを開封・使用できるため、場所を問わず使いやすく、贈る側も相手の住所や在宅状況を気にせず渡せるのが大きな魅力。近年では、従業員へのインセンティブや記念品としても、企業から選ばれるシーンが増えています。
福利厚生領域でデジタルギフトが注目されている理由
従来の福利厚生では、「全社員に同じものを配布する」「紙のチケットを手渡しする」など、一律・手間・保管管理の煩雑さが課題でした。その点、デジタルギフトは「自由に選べる・即時配布できる・管理がラク」という点で、現代の多様な働き方や社員ニーズにマッチします。
特にリモートワークや多拠点勤務が進む今、物理的な距離を超えて“想いを届けられる”福利厚生として支持されており、従業員満足度の向上施策として導入する企業が急増しています。
さらに、ギフトの内容も食事・日用品・育児アイテム・エンタメまで幅広く、年齢やライフスタイルを問わず“選べる楽しさ”を提供できるのも大きな特徴です。
.jpeg?w=1200&h=800)
福利厚生にデジタルギフトを導入するメリット
従業員側のメリット
1. 自分のライフスタイルに合わせて“選べる”
社員それぞれが、家族構成や生活リズム、価値観も異なる中で、自分にとって本当に嬉しいギフトを選べるのは、非常に大きな満足要因です。
「コーヒーをよく飲む人」「子育て中の人」「一人暮らしで食事重視の人」など、それぞれの“今欲しいもの”に応えられるのがデジタルギフトの強みです。
2. 受け取りが簡単で、好きなタイミングで使える
スマホやPCでURLを開くだけで、ギフトをすぐに受け取れるため、郵送物を待ったり会社に出社したりする必要がありません。また、有効期限が長いギフトも多く、自分のタイミングで使える自由度が社員にとってストレスフリーなポイントです。
3. 福利厚生への“納得感”が高まりやすい
「せっかくの福利厚生だけど、使わなかった」「もらったけど要らないものだった」といった“もったいなさ”や不公平感を、デジタルギフトは回避できます。選択の自由があることで、納得感・満足感が自然と高まり、企業への信頼や愛着にもつながります。
企業側・人事担当者のメリット
1. 配布・管理がスムーズで業務負担が軽い
紙のチケットや現物ギフトのように、「在庫管理」「配布ミス」「郵送手配」などの手間がかかりません。メールや社内チャットで一括配布でき、配布履歴もデジタルで管理可能。人事・総務の負担を大幅に軽減できます。
2. 社員データに基づいた柔軟な設計が可能
社員の部署・勤務地・職種・勤務形態に応じて、金額やギフト内容を柔軟に出し分けられるのもデジタルギフトならでは。たとえば、リモート勤務者にはオンライン特化ギフト、オフィス勤務者には飲食系チケットなど、パーソナライズ施策が実現しやすくなります。
3. コスト管理・福利厚生費の透明化に寄与
ギフトごとに使用状況や未使用分を可視化できる管理機能を備えたサービスも多く、無駄のない運用・コスト最適化が可能です。また、福利厚生費としての処理もしやすく、会計面でも企業メリットが大きいのが特徴です。
社員が喜ぶデジタルギフトの選び方
デジタルギフトの主な種類
デジタルギフトにはさまざまなタイプがあり、用途や贈る相手の属性に応じて柔軟に選べます。福利厚生として活用する際は、「選択肢の豊富さ」「使いやすさ」「誰でも嬉しい汎用性」がポイントになります。
種類 | 内容・特徴 |
|---|---|
ポイント型ギフト | 汎用性のある金額分のポイントを付与し、後から好きな商品と交換。用途が幅広く、運用しやすい。 |
カフェ・コンビニチケット | ドリンク・スイーツ・軽食など。日常で使える気軽さが魅力で、使い忘れも起きにくい。 |
食事・デリバリーギフト | 宅配・デリバリーやレストラン系など、“食”に関する充実ラインナップ。健康支援や福利厚生費化にも対応。 |
日用品・雑貨系ギフト | 消耗品や生活雑貨など、日々の暮らしに役立つアイテムを自由に選べるギフト。 |
エンタメ・娯楽系 | 動画・音楽・電子書籍などのサブスクや体験ギフト。オフタイム充実に貢献し、QOL向上をサポート。 |
選べるギフト | 複数のジャンル・ブランドから受け取り手が好きな商品を選べる形式。自由度が高く、万人受けしやすい。 |
選び直せるギフト | ギフト開封時に「やっぱり別のものにしたい」が可能な柔軟設計。社員の心理的負担を軽減し、体験満足度が高い。 |
社員に“本当に喜ばれる”デジタルギフトを選ぶためのポイント
1. 「誰でも使えるか?」を重視する
年齢・性別・家族構成に関係なく、誰にでも喜ばれるギフトであるかは福利厚生の公平性に直結します。迷ったときは、「選べるギフト」や「日常使いできるチケット」が鉄板です。
2. 利用シーンを具体的にイメージする
「テレワークの合間に」「子どもとの週末に」「自分へのちょっとしたご褒美に」など、社員の生活に自然と溶け込むかどうかも重要な判断軸。使い道が思い浮かびやすいギフトは、使用率や満足度も高くなります。
3. 好みが分からないときは“選べるギフト”“選び直せるギフト”が安心
福利厚生で社員全体にギフトを配る場合、「全員に合うものを選ぶ」のは簡単ではありません。特に、好みや生活スタイルが見えにくい時ほど、“選べる・選び直せる”柔軟性が重要です。
開封後に「やっぱり別のものにしたい」と選び直せるデジタルギフトなら、そのときの気分やニーズに合った選択ができ、不満や使われないリスクも軽減。一律配布でもパーソナライズされた体験が叶う点が、多くの企業に選ばれる理由です。
関連:もらって嬉しい“選べるギフト”特集!今話題の選び直せるソーシャルギフトも紹介
従業員満足度を高めるデジタルギフトの活用シーン
誕生日・記念日などのパーソナルなお祝いに
社員の誕生日や入社記念日など、個人に合わせたお祝いのタイミングに、オンラインで手軽に贈れるデジタルギフトは最適です。離れていても気持ちが伝わりやすく、ちょっとした特別感を演出できます。
表彰・社内アワードの副賞として
成果を称える場面で、表彰状だけでなくその場ですぐ届くデジタルギフトを添えることで、受け取る側の実感が強まります。手間なく渡せるのに、印象に残る表彰体験になります。
繁忙期後のねぎらい・リフレッシュ施策に
「おつかれさま」「ありがとう」の気持ちを、ワンクリックで届けられるのがデジタルギフトの強みです。忙しさのあとにタイミングよく贈ることで、気持ちの切り替えや満足度向上につながります。
永年勤続のお祝いに
節目の年数を迎えた社員への表彰ギフトとして、記念品に代わる新しい選択肢としてデジタルギフトが活躍します。開封時に選び直せるタイプなら、その人らしい満足度の高い贈り方ができます。
創立記念・周年行事の全社ギフトとして
創立記念日や周年イベントなど、全社員へ感謝を届けたいタイミングでも、デジタルギフトなら即時かつ一括で配布できます。一律配布でも自由に選べる仕組みがあれば、満足度のバラつきも抑えられます。
非正規雇用社員への感謝ギフトとして
賞与対象外となるアルバイトや契約社員にも、「ありがとう」の気持ちを公平かつ気軽に届けられるのがデジタルギフトの利点です。雇用形態に関わらず感謝を伝えることが、信頼や定着にもつながります。
関連:コーポレートギフトおすすめ15選!シーン別選び方&最新トレンド解説
デジタルギフト導入時の実務ポイント|注意すべき落とし穴と対策
課税対象になるケースと福利厚生費として処理できる条件
デジタルギフトを福利厚生の一環として支給する場合、気をつけたいのが課税・非課税の取り扱いです。
一定の条件を満たせば「福利厚生費」として非課税で処理できますが、運用の仕方によっては給与課税の対象になる可能性もあります。
例えば、特定の社員のみに高額なギフトを渡したり、評価・成果に応じた支給として位置づけた場合は、「給与」や「賞与」とみなされ、所得税や社会保険料の課税対象となる恐れがあります。
一方で、全社員に一律で提供されるギフト(季節的な贈り物や記念品など)であれば、福利厚生費として非課税扱いにできるケースが多いとされています。
また、金額が過度でないこと、個人的な対価性がないこと、社内規定に基づいて支給されていることなども重要な判断材料です。
制度導入時には、社内ルールの整備や、税理士・社労士への事前相談をおすすめします。適切な設計によって、税務リスクを抑えつつ、社員にも安心して喜ばれる福利厚生が実現できます。
配布方法と対象者の選定ルールが曖昧になっていないか
「誰に・いつ・どのように配布するか」が不明瞭なままだと、社員間での不公平感が生まれる原因になります。たとえば、業績や勤続年数に応じた配布なのか、全社員一律なのか。ルールが曖昧だと「なぜ自分はもらえなかったのか」という疑念を生むこともあります。事前に社内で方針を共有し、配布基準を明確にしておくことが大切です。
ギフト未使用・未開封の管理が放置されていないか
せっかく贈ったデジタルギフトも、使われなければ意味がありません。未開封のまま期限切れになったり、使用率が低いままだと、社内での制度の評価も下がってしまいます。定期的に利用状況を確認し、使われていない場合はリマインドを行うなど、運用後のフォローも重要なポイントです。
“選び直せる”が喜ばれる理由|今注目のデジタルギフト
「選び直せるギフト」は、贈り手が1つのギフトを選んで贈り、受け取り手がそのギフトをそのまま受け取るか、同価格以下の別のギフトに選び直すことができる新しいギフトの形です。
この仕組みにより、贈り手は相手を想ってギフトを選ぶという気持ちを伝えつつ、受け取り手は自分の好みや状況に合わせて最適なギフトを選ぶことができます。

選び直せるデジタルギフトが福利厚生で人気の理由
選び直せるギフトが注目されている背景には、贈る側・受け取る側の両方にとっての“ちょうどよさ”があります。
受け取り手の満足度が高い
受け取った相手は、ギフトの内容を確認した上で「そのまま受け取る」か「他のギフトに変更する」かを選べるため、より自分に合った贈り物を手にできます。結果として、使ってもらえる確率も高くなります。
送り手の気持ちが伝わりやすい仕組み
従来の“カタログ型”のように「たくさんの中から自由に選んでね」ではなく、まずは送り手が相手を想って1つのギフトを選ぶというプロセスがあるため、ギフトに込めた気持ちがきちんと伝わりやすくなります。
そのうえで受け取り手の都合に合わせて変更できるので、“思いやり”と“自由”のバランスが非常に良いのです。
贈り手にとっても安心感がある
相手の好みが分からない、気に入ってもらえるか不安。そんな迷いがある場面でも、選び直せる仕組みがあれば気軽に贈れます。「もし違ったら変更できる」という余白が、贈る側の心理的なハードルを下げてくれます。
このように、「選び直せるギフト」は贈る人の想いをしっかり伝えつつ、受け取る人の満足度と自由も尊重できる、新しいギフトの形として広がりつつあります。
福利厚生領域におけるデジタルギフトの活用事例
選び直せる法人ギフトは、贈る側・受け取る側双方にメリットがあり、様々な企業で導入が進んでいます。今回はその活用事例をご紹介します。
株式会社ホットリンクの利用事例 [社員への永年勤続表彰]
従業員の満足度向上と感謝の気持ちを伝えるため、ホットリンクは永年勤続表彰にGIFTFULを導入。受け取り手が自分の好みに合わせてギフトを選び直せる仕組みが好評で、従業員本人はもちろん家族の笑顔にもつながりました。さらに、お礼メッセージを通じたコミュニケーションの活性化や、準備工数の削減といった効果も実感。これまでの“贈るだけ”の表彰から、心が通う体験へとアップデートされています。従業員も家族も笑顔になるギフトを。ホットリンクが永年勤続表彰を刷新した理由| GIFTFUL体験談
株式会社HubOneの利用事例 [社員への福利厚生ギフト]
株式会社HubOneは、フルリモート体制の中でメンバーとの関係性を深めるため、従来のギフトカードからGIFTFULに切り替えました。贈り手がギフトを選び、受け取り手が同価格以下の他のギフトに変更できる仕組みにより、メンバーからの感謝のメッセージや会話が生まれ、コミュニケーションが活性化。また、ギフトの受取状況や返信内容を通じて、メンバーのモチベーションや関心を把握する手段としても活用されています。GIFTFULは、贈り物を通じてリアルなつながりを築く有効なツールとなっています。社内から続々と届いた喜びの声。メンバーへの贈り物を通じて生まれたリアルなコミュニケーション| GIFTFUL体験談
白潟総合研究所株式会の利用事例 [社員への誕生日ギフト]
社員の誕生日に金券を贈っていましたが、会話が生まれるわけでもなく、ただ渡すだけになっていました。もっと想いが伝わる方法を模索する中で、GIFTFULを活用し始めました。
実際に使ってみると、社員から直接「ありがとう」と言ってもらえる場面が増え、感謝の気持ちを届けられたという実感があります。年齢や性別に関係なく、相手が自分でギフトを選び直せる仕組みも大きな安心材料でした。
今この瞬間、一緒に働いてくれることへの感謝を、ギフトという形で自然に伝えられています。社員の心に届く贈り方|GIFTFULで変わった誕生日のコミュニケーション
まとめ|福利厚生で従業員満足を高めるなら、デジタルギフトという選択肢を
多様な働き方が広がる中で、社員一人ひとりに寄り添った福利厚生が求められています。その実現に有効なのが、柔軟に贈れて、好みに合わせて使えるデジタルギフトです。記念日や表彰、ねぎらいのタイミングで、気持ちと一緒にギフトを届けることで、従業員満足度を自然に高めることができます。
「社員が本当に喜ぶ福利厚生を届けたい」と感じたら、選べる・選び直せるギフトが揃った「GIFTFUL」をぜひチェックしてみてください。贈る人も、受け取る人も、気持ちよくつながれる仕組みがここにあります。

関連記事▼
法人ギフトとは?ビジネスシーン別に選び方・人気ギフトを解説
おしゃれな周年祝い77選|お菓子や花などセンスがいいギフトを厳選紹介
もらって嬉しい景品ランキング!200人調査を元にイベント・予算別に人気景品を紹介
選び直せるギフト
贈り手が1つ選んで贈り、
受け取り手は選び直しもできる
新しいギフトサービスです。

・複数ギフトをカンタン一括発行
・企業ロゴ入りメッセージカード
・受け取られなければお支払いゼロ

