あの人のボールペン - カツセマサヒコ「もらったものが私をつくる」第3話
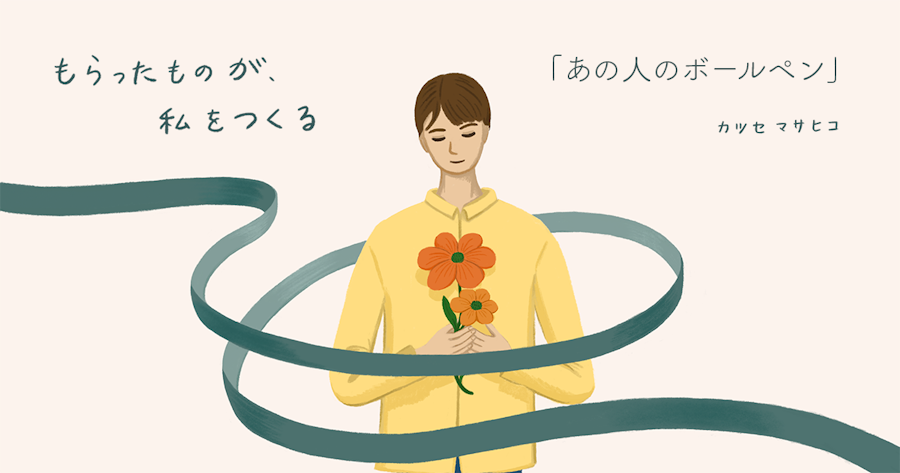
「もらう」よりも「あげる」ほうがなんだか嬉しくて、でもその気持ちは、もしかして「くれた人」に失礼なんじゃないかって思ったりする。
もらったものが気に入らなくて「なんだこんなもの」と憤りすら感じていたのに、後になってそれに込められた気持ちに気付いてようやく愛情を噛み締めたりもする。
カツセマサヒコが描く、“ギフト”にまつわる不器用な人間たちによる一話完結の物語『もらったものが、私をつくる』。第三回は、職場に苦手な先輩がいる女性の話。
あの人のボールペン
誰にだってそりが合わない人はいる。そう信じていないと、自分が卑屈な人間に思えて耐えられなくなる。今回だって、たまたま新卒で入った会社の先輩が自分とは合わなかった。それだけのこと。
そう言い聞かせていても、やっぱり毎日顔を合わせる人と相性が悪いっていうのは、どうにもストレスがかかる。先輩が隣に座るたび、喉の奥に針が落ちるような、研磨された緊張感が全身を走る。なんとか自然に会話ができないか、笑い合えるような関係になれないかと手を尽くそうとするけれど、もう自分じゃどうにもならないくらい、会話が続かず、ヘマもする。
「この書類、見直した?」
「あ、えっと、はい」
「ここ、日付が違ってる。あとここ、数字が去年のままになってる。ここも」
「わ、あ、すみません、すぐ直します!」
「あと、先週頼んだやつって、もう送ってくれた?」
「え? ……あっ!?」
「それ、先にやっといて」
私の仕事は何一つ信用されておらず、書類はウンザリするほど細かくチェックされ、進捗も口うるさいほど確認される。そして見事に、先輩の指摘は当たってしまう。コイツはダメなやつ。そう思われている気がすると、作業はどんどんスピードが落ちて、見直したはずの書類からいくつもミスが溢れ出る。先輩は重たそうな赤いボールペンを使っていて、その赤いインクが、今日も私の書類に色を付ける。
ほかの先輩との仕事はそこまでミスもしないのに、なぜか、よりによって、教育係となっている先輩にだけ、そうしたネガティブな連鎖を断ち切ることができない。入社当時は昼食も一緒に食べていたのに、二ヶ月前に「今日は同期と食べてきます」とうそぶいてから、私は一人でお弁当を食べるようになった。
「この仕事、やってる意味がわからないんですけど」
先輩からとある仕事を引き継いでいるとき、その内容があまりに機械的かつ抽象的すぎて、思わず先輩にそう口走ってしまったことがあった。無知で何もわかっていなかったとはいえ、確かにその仕事は、わざわざ大学を出てまでして入社した自分がやるにはやりがいがなさすぎるように思えた。
「あなたにとって意味がないと思えることが、誰かにとっての大きな助けとなることがある。その場では報われないかもしれないけど、私たちは、そういう仕事をしてるんだと思うよ」
この先輩とうまくやれたらな、と純粋に願う自分と、この先輩さえいなくなってくれたらな、と残酷に想像する自分が、静かに頭の中で溶け合っている。会社近くの公園で食べるお弁当は、いつも湿気っているような味がした。
*
「では、お世話になりました」
そんな先輩が異動することになったのは、私が入社して三年が経った頃だった。まさか、本当に? 突然の辞令に、私はこの日を想像してしまった自分を呪った。もしも私があんな想像をしていなければ、先輩は異動せずに済んだんじゃないか。そう思うと、心が石化していくような苦しみが湧いて、止まなかった。
結局、別れの際までうまく話せないまま先輩は異動していって、私もいつの間にか、教わる立場から教える立場になった。先輩の穴を埋めるようにして、新入社員が入ってきたのだ。
「僕、この会社の古い体質とか、変えようと思ってるんで」
入社三ヶ月のリクルートスーツ上がりの男の子は、大学の四年間でたっぷりと吸い込んだ成功体験によって、自尊心に満ち満ちていた。初めての後輩は疲弊しきった私には眩しすぎる存在で、こんなやつが来るくらいなら、あの先輩と一緒にいた方が何倍も良かったと、今更思ったりもした。こちらが教えようとした仕事も、聞いているんだか聞いていないんだか、ぼんやりとした返事しかせず、メモすら取らない子だった。
イライラした。そのイライラがどこからくるかと考えてみれば、ああ、これ、自分自身なんじゃん、と不意に理解した瞬間があった。彼が誰かに似ている気がして、それが入社したばかりの頃の自分だと思うと、途端に恥ずかしくなり、思わずデスクから立ち上がってしまっていた。
私、こんな態度であの先輩に接していたのか。入社したばかりのくせに、この子と同じようにキラッキラした目で、出来もしないことばかりを口にして、目の前の仕事は蔑ろにして、偉そうにふんぞり返っていたのか。
急に、いなくなった先輩の発言や仕草が、脳内でいっぺんに花が咲くように広がった。
あの先輩は、私が社会でしっかりと生きていけるように、必死にいろんなことを教えようとしてくれていたんだ。もうこのオフィスにはいなくなった先輩の温かさが、今になって身に染みて、謝りたい言葉や感謝の気持ちが自分からじんわりと溢れていくのを感じた。
「僕、この仕事に意味があるとは思えないんですけど」
まるで当時の私と同じように、同じ仕事で、同じタイミングで、私にとって初めての後輩がそう言った。そして、その言葉が出てくるのを、私自身も待っていたのかもしれない。
「あなたにとって意味がないと思えることが、誰かにとっての大きな助けとなることがある。その場では報われないかもしれないけど、私たちは、そういう仕事をしてるんだと思うよ。って、好きだった先輩に言われたことがあったんだ」
あの先輩に、なんの恩返しもできなかった。だからこそ、あの先輩からもらったたくさんの言葉と真摯な姿勢を、次の後輩に繋いでいきたい。それくらいなら、私にもできるかもしれない。
そう思うと、やりがいを感じられなかった仕事たちが、ようやく少しずつ呼吸を始めたように感じられた。意味がないと思っていた仕事が、どのような意味を持ってそこにあるのか、今は一つひとつ答えられる。あの先輩に、今の私を見てもらいたくなった。
「でも、時代は流れていて、君の言うように本当に意味がない仕事も、残ってるかもしれない。だから今みたく、本当に意味があるのかを疑うのは大事だと思うよ」
あのとき、先輩に言われた言葉に、ほんの少し、自分の言葉を足していく。そうして受け継がれてきたギフトが、きっとどの職場にもあるんだろう。そしてどうか、私の後輩となったこの子もまた、誰かにそれを引き継いでいってほしい。そんなことを思いながら、今日は早めに仕事を切り上げた。帰りに文房具屋で、あの先輩が使っていた重たそうなボールペンを買って帰ろう。それでまた明日から、少しずつ先輩に近づく努力をしていこう。陽が落ちて存在感を強くしたオフィス街の明かりを眺めながら、そんなことを思った。
作者プロフィール
カツセマサヒコ
小説家
1986年東京生まれ。2014年よりライターとして活動を開始。2020年『明け方の若者たち』(幻冬舎)で小説家デビュー。同作は累計14万部を超える話題作となり、翌年に映画化。2作目の『夜行秘密』(双葉社)も、ロックバンド indigo la Endとのコラボレーション小説として大きな反響を呼んだ。他の活動に、雑誌連載やラジオ『NIGHT DIVER』(TOKYO FM 毎週木曜28:00~)のパーソナリティなどがある。
LINE公式アカウントをお友だち追加するとギフトにまつわる心あたたまるストーリーを受け取れます。
選び直せるギフト
贈り手が1つ選んで贈り、
受け取り手は選び直しもできる
新しいギフトサービスです。
