笑ってくれたんじゃなくて、笑われていた。 - カツセマサヒコ「もらったものが私をつくる」第2話
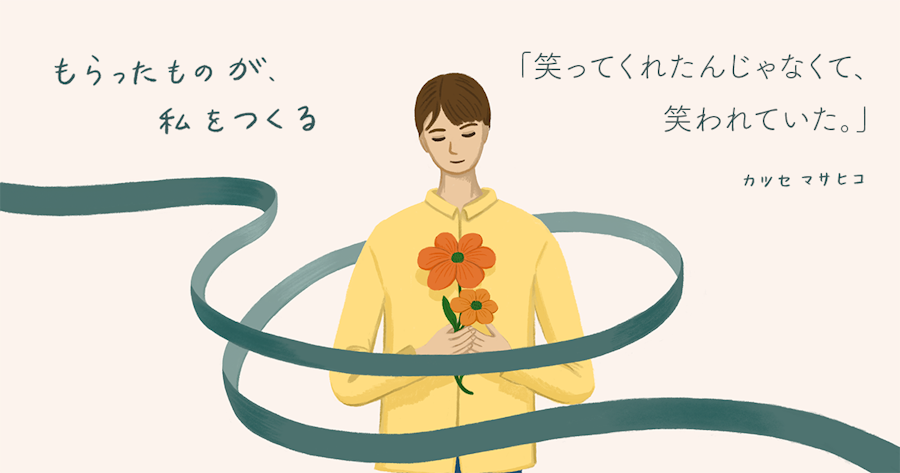
「もらう」よりも「あげる」ほうがなんだか嬉しくて、でもその気持ちは、もしかして「くれた人」に失礼なんじゃないかって思ったりする。
もらったものが気に入らなくて「なんだこんなもの」と憤りすら感じていたのに、後になってそれに込められた気持ちに気付いてようやく愛情を噛み締めたりもする。
カツセマサヒコが描く、“ギフト”にまつわる不器用な人間たちによる一話完結の物語『もらったものが、私をつくる』。
第二回は、せっかく渡したプレゼントを気に入ってもらえなかった男子の話。
笑ってくれたんじゃなくて、笑われていた。
今でも恥ずかしくて思い出したら受験勉強どころじゃなくなっちゃうのが去年の秋の大失態の記憶だ。何もわかっていなかった僕も悪いけれど、あそこまで笑い者にした彼女たちへの嫌悪感も消えやしない。全ては高校二年のとき、木田奈那と同じクラスになったことがいけなかった。
木田奈那は、僕の一つ前の席にいた。「木田」と「木ノ下」だから、単純に木田の出席番号が僕より一つ前だったって話だ。木田の肩の下まで伸びた髪はクラスの中でも一際明るく、その毛先は揺れるたびにどことなくいい匂いがした。彼女の声は授業中も休み時間も華やかな存在感を発揮していて、世界は(つまりクラスは)彼女を中心に回っているようにすら思えた。
対照的に、僕は空気になってしまうことが得意な人間だった。無色透明、人畜無害。なるべく事を荒立てず、長いものには積極的に巻かれてしまうことで生き延びた人生だった。エレベーターでカップルと相乗りになると、僕の存在などそこにないように激しくキスを始めたり抱き合ったりされることが多かった。気配がなく、幽霊みたいだと言われることすらあった。
だから、「木田奈那がお前に好意を抱いているらしいぞ」とクラスメイトの黒岩から言われた時、何かの間違いじゃないかと思った。木田は確かに授業中や休み時間によく話しかけてくれていたけれど、僕よりもっとモテそうな、それこそサッカー部の先輩とか、そういう人と付き合ってるものかと思っていた。しかしよくよく思い返せば木田に関する恋愛関係の噂は一切聞いたことがないし、黒岩の情報によれば恋人もしばらくおらず、意外と恋には積極的ではないらしい、とのことだった。
あの木田奈那が、僕のことを?
人間とは単純なもので、一度でも相手を恋愛対象として認識してしまうと、すぐにその人を「そういう目」で見るようになってしまう。僕らは席替えによって机が離れてからも頻繁に会話をするようになり、何度か一緒に帰ったりもした。クラスでそういう関係の男女は周りでもあまり見なかったし、その時間がどれほど楽しかったものか、今となっては当時の二人が羨ましいとすら思う。
僕らは会話の波長が妙に合った。木田がコミュ力おばけってこともあるかもしれないけれど、僕は木田以外の女子と話すときには緊張するのに、木田に対してはいくらでも自然体で接することができた。
「なんか木ノ下くんといると芸人みたくなっちゃうんだよねえ。私いつもは全然こんなじゃないのになあ」
「わかる。俺も木田といると、そんな感じ」
それでも付き合うまでに至らないのは、果たして自分は木田の恋人になりたいと思うほど好きなのか、恋愛についての確信をいまいち持てないからだった。木田は過去に何人かと付き合っていたらしいけれど、僕はあれから一年経った今も、恋人ができたことはない。それゆえ、告白のタイミングやらなんやらが、いろいろとわからなかった。木田とずっとこういう関係でいられたら。いや、それ以上に親密な関係になれたらと思う瞬間は山ほどあったけれど、告白をして、恋人として付き合う。その未来はなぜか想像がつかなかった(これは強がりでも格好つけているわけでもなく、本心でそう思っていたのだ)。
恋人にならなくたって、木田のことを一番に想う人間にはなれる。
そう信じていたから、僕は彼女に尽くすこともできたのだと思う。いつだって木田が喜ぶ顔を見たかったし、木田を喜ばせられるのは自分だと、どこか確信めいたものを持っていた。
その勘違いが、悲劇を生むことになったのだ。
10月、秋が深まりはじめ、学校から見える山の景色もうっすらと赤みを帯びた頃だった。木田がまもなく誕生日を迎えることを(SNSで)知った僕は、クラスメイトの黒岩と誕生日プレゼントを買いに出かけた。アドバイスを求めるつもりで誘った黒岩は、僕と同様にこれまで一度も恋人を作ったことがない人間であったが、人数は多い方がプレゼントを悩む時間は減るだろうと踏んで同行してもらった。
「クラスメイトってことは、一緒に勉強する仲間だろ。そしたら、文房具が一番無難なんじゃないか?」
「たしかに。指輪なんて絶対に重たいし、コスメなんてわからないし。文房具だったら、イヤラシサもなく渡せそうだな」
そんな小さな作戦会議をして、黒岩とショッピングモールの中に入っている雑貨屋に向かった。「まだ付き合っておらず、だが最も仲の良い異性のクラスメイト」に送るプレゼントとして、その雑貨屋の商品は値段、質、センス、全てにおいてちょうどいいだろうと話した末の選択だった。文房具エリアに着くと、ペンや紙、消しゴム、ハサミ、ファイルや工具類まで、それぞれ数十種類ものバリエーションを持って陳列されており、ふと見上げれば「地域最大級の品揃え!」とド派手な看板がぶら下がっていた。
ここまで膨大な量の選択肢から、木田にふさわしいものを選ぶのか。途方もない作業に思えた。しかし、プレゼントとはこの「選ぶ時間」にこそ価値があるのだと、黒岩は説いた。長く時間をかけて選んだものにこそ、想いは込められていくのだと、黒岩は腕を組みながら力強く言った。僕はまんまと黒岩の言葉を鵜呑みし、四時間かけて、一つのメモパッドと三種類の消しゴムを選んだ。メモパッドにはこれまで見たことはないが確実に誰もが可愛いと言うであろうヒヨコのキャラクターが描かれており、消しゴムは木田と一緒に食べたことがあるハンバーガーの形やエビフライの形をしたものにした。
レジで簡易的なプレゼント包装をしてもらって、準備は整った。黒岩は二時間ほど経過した時点で「塾がある」と言ってリタイアしてしまったが、僕は文具売り場での四時間分の想いを、プレゼントに存分に込めることに成功した。
そして迎えた、木田の誕生日当日。一時間目の授業が終わったタイミングで木田の席に向かい、プレゼントをそっと机の上に置いた。
「え、なにこれ」
「あー、誕生日でしょ。おめでと」
「え! 本当に!? ありがとう〜!」
木田はその場で包装を破り、メモ帳と消しゴムを見て、とても嬉しそうに笑った。なんならいくつかモノボケまでかましてくれたほどで、ああ、よかった、きちんと想いは伝わったのだと思った。教室の隅の席から見守ってくれていた黒岩も、満足そうに何度も頷いた。プレゼントと一緒に、ちょっとした手紙も渡した。このプレゼントを選ぶに至った経緯と、選ぶのに四時間かけたことを書いた。その手紙は後で読んでくれと伝えて、僕は席に戻った。
平静を装っていたけれど、内心、緊張と興奮で、どうにかなってしまいそうだった。あんなに喜んでくれたなんて、選んでよかったと本気で思った。黒岩にも感謝しなければならない。今度ジュースでも奢ろうと思いながら、次の授業の準備を始めた。問題が起きたのは、その夜だった。
「四時間かけてアレとか、マジでキモいんだけどw」
「てかなに、あのヒヨコw 小学生かww」
「私てっきりグッチのキーケースとかもらえると思ってたw」
「ないわーマジでないわーw」
僕が見ていた木田のSNSアカウントは、クラスのみんなが知っているものとは別の、隠された匿名アカウントだった。いつも木田と遊んでいる女子メンバーだけがフォローしており、全員が匿名になって、しかし鍵はかけずに、リプライを飛ばしあっていた。
僕がそのアカウントまで見ていることを、木田は知らなかったんだろう。仲良しメンバーの間で共有されたらしい僕の手紙とプレゼントは、見事に笑いものにされてしまっていた。笑ってくれたのは、嬉しかったからじゃなくて、変だったからなのだ。
僕はベッドの上で布団に顔を埋めながら、何度も何度も叫び声を上げた。そうでもしていないと、あまりの恥ずかしさにどうにかなってしまいそうだったからだ。足をバタバタとマットレスに叩きつけながら、自分の行動を恨んでは、また叫んだ。叫び続けて、もうその記憶とは、できるだけ距離を置いて生きるしかないと思った。
あの日から今日まで、木田からは距離を置かれたまま、そして僕も木田たちには近づかないようにしながら、なんとか高校生活を送っている。受験まであと数ヶ月。卒業してしまえば、あの失態も少しは影を潜めてくれるだろう。そう信じながら、今は勉強を頑張るしかない。悲しい思い出になってしまったけれど、いつかこれすら笑い話にできる日が来ることを願っている。
作者プロフィール

カツセマサヒコ
小説家
1986年東京生まれ。2014年よりライターとして活動を開始。2020年『明け方の若者たち』(幻冬舎)で小説家デビュー。同作は累計14万部を超える話題作となり、翌年に映画化。2作目の『夜行秘密』(双葉社)も、ロックバンド indigo la Endとのコラボレーション小説として大きな反響を呼んだ。他の活動に、雑誌連載やラジオ『NIGHT DIVER』(TOKYO FM 毎週木曜28:00~)のパーソナリティなどがある。
LINE公式アカウントをお友だち追加するとギフトにまつわる心あたたまるストーリーを受け取れます。
選び直せるギフト
贈り手が1つ選んで贈り、
受け取り手は選び直しもできる
新しいギフトサービスです。
