甘くなくても構わない - カツセマサヒコ「もらったものが私をつくる」第10話
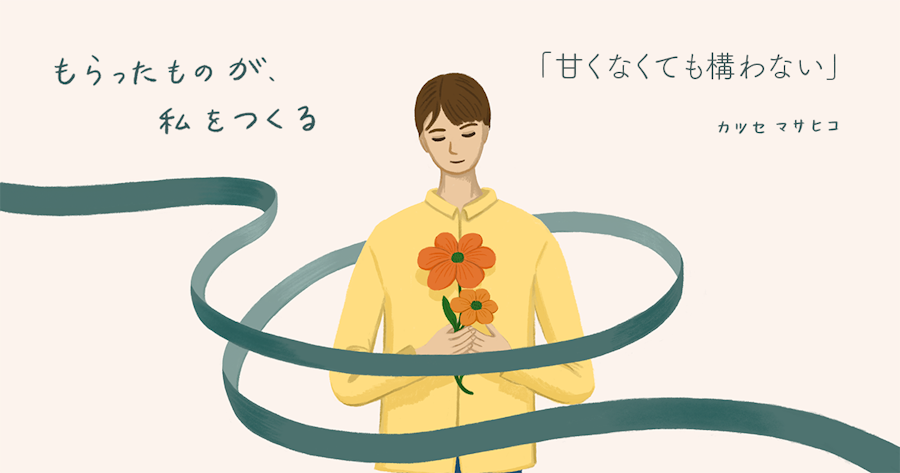
「もらう」よりも「あげる」ほうがなんだか嬉しくて、でもその気持ちは、もしかして「くれた人」に失礼なんじゃないかって思ったりする。
もらったものが気に入らなくて「なんだこんなもの」と憤りすら感じていたのに、後になってそれに込められた気持ちに気付いてようやく愛情を噛み締めたりもする。
カツセマサヒコが描く、“ギフト”にまつわる不器用な人間たちによる一話完結の物語『もらったものが、私をつくる』。
第十回は、とある夜に公園で待ち合わせた高校生の話。
甘くなくても構わない
錆びたブランコがキィキィと音を立てて、緩やかに私を揺らす。両手でチェーンを掴むと、あらゆる冷気の始まりのような痛みが手に宿った。隣の松田は、それも気にならない様子でブランコを静かに揺らし続けている。辺りは夜に飲まれ、公園を寂しそうに照らす街灯は、松田の表情を曖昧にしか映してくれない。
「真っ暗だ」
「ね」
「そろそろ、帰るけど」
「あ、うん」
松田が静かに立ち上がって、黒のエナメルバッグを肩にかけた。私もすぐにその後を追って、地面に放っていたリュックサックを背負う。このリュックの中に、今日松田をここに呼び出した理由が入っていることを、改めて意識する。
「松田ぁ」
車やバイクが入って来られないようにバリケードを施した公園の入り口を、松田が川の水のように緩やかにすり抜けていく。咄嗟に名前を呼んだものの、次の言葉が出てこない。
「どした?」
沈黙が私たちの間を横切り、居座る。それでも松田は不機嫌な様子を見せず、むしろこの静寂を堪能するかのように、ゆっくりと瞬きして私を見た。呼び出したのは私なのに、この公園で三十分近く黙っている私に、一言も苦言を呈することなく一緒にいてくれている。申し訳なさに心が痛む一方で、そういうところが好きなのだと確信する。ほかの男子みたいに、変に話題を探したりせず、焦らず、静寂を音楽のように楽しんでくれる。ほかの男子といても、こんなに沈黙が気にならないことはなかった。
私は背負っていたリュックを前にかけると、奥の方に眠らせていたチョコレートを手に取る。昨日、大苦戦しながら作った自作のチョコレート。この公園を出てしまったら、きっともう渡す機会は訪れないだろう。松田は学ランの上にマフラーしか巻いておらず、コートなどは着ていない。見ているだけで寒そうなのに、身震い一つせずに、私を見つめてくれている。
「あ、えっと」
「うん」
包装紙に包んだチョコレートを、一息で取り出す。そのまま両手で持つと、松田の前に、突き出した。
「チョコです。受け取ってください」
それから松田の返事が聞こえるまで、時間にして3秒ほどだったはずなのに、自分の中に流れていたはずの時は静かに止まって、世界に私ひとりしかいなくなってしまったかと思うほど、ふいに松田の存在が感じられなくなった。だから次の言葉が聞こえたとき、その内容が予想外だったことより先に、松田が返事をしてくれたという事実だけでまずはいくらか安心してしまったのだった。
「俺、チョコ食べられないんだ」
顔をあげると、松田は本当に申し訳なさそうに眉をハの字にして、両手を胸の高さまで上げて降参するようなポーズを取っていた。
「え?」
「甘いの、苦手なん」
「え、ほんとに?」
チョコを渡すことすら断られることって、あるの? 私は予想もしていなかった返事に狼狽し、じゃあこの差し出したチョコレートはどうしたらいいのか、真っ白になりつつある頭の中で必死に考えていた。どうする。どうしたらいい?
「それは、あげるからさ」
松田はどこか申し訳なさそうに眉間に皺を寄せた。
「その代わり、たこ焼き食いたくて。付き合ってくんない?」
「え?」
「俺、むっちゃ腹減ってんの、今」
「あ、え、今から? たこ焼き行くの?」
「うん」
何それ、かわいい。
松田は私の返事を待たずに公園を出ると、すぐ横に停めてあった自転車に跨った。
「駅前んとこ行くから、後ろ、乗ってって」
「え」
まるで、夢か魔法か、安っぽい妄想みたいだった。まだ告白もできておらず、そもそもチョコすら受け取ってもらえていないのに、松田は私を自転車の後ろに乗せて、ゆっくりと風を切って道を進んだ。夜の冷えた空気が服の隙間から入り込んできて、ぎゅっと体を小さくすると、松田の背中の大きさがより際立って感じられた。
「やべ」
五分ほど無言で走ったところで、松田が低く唸るように声を出した。なにか問題が起きたのか、松田の肩越しに前方を覗こうとしたところで、視界の隅に見覚えのある姿が飛び込んだ。私たちの乗る自転車は、歩いていた警察官の真横を通り過ぎたのだ。
あ、捕まる。と思った直後、警察官は私たちの背中に向かって「気をつけろよなー」とだけ、退屈そうに言った。
「うは、許してくれんの、ウケる」
松田が思わず吹き出して、私もそれにつられて笑った。
「本当。すごい奇跡」
なんだか、今は全部が青信号なのだと、そんな気がした。こうして二人でたこ焼き屋に向かう間、私たちはすべてに祝福されていて、追い風ばかり吹いているのだと、根拠もないけれど、そんな確信めいた感覚だけがあった。
駅前のスーパーに併設されたたこ焼き屋には、私たち以外誰もお客さんがいなかった。店舗自体は小さいけれど、味は確かでリピーターが多い。地元客に愛されすぎていて、私は逆に近づきにくくなっている場所だった。松田は今でもこの店によく通うようで、その証拠に、「今日もオマケしておくね」とおばちゃん店員さんから笑顔を振り撒かれていた。
「あ、ここは出すよ。バレンタインのつもりだったから」
レジに表示された金額を見て財布を取り出そうとした松田に、声をかける。
「いや、俺がたこ焼き食いたいって言っただけだから」
「でも、私からはなんも渡したことにならないじゃん」
「でも、ここでもらったら、さっきのチョコと合わせて、金も手間も二倍かかっちゃうよ?」
「いいよ。二倍美味しそうな顔してよ」
「なんそれ」
半ば強引にお金を支払うと、店の前に置かれたベンチに二人で並んで、たこ焼きを頬張った。猫舌の松田は美味しそうに食べるのがどうにも下手らしく、そんなところも愛おしくて、見ていて温かいお湯に浸かるような、穏やかな気持ちになる。
それで、ふと思う。私は、手作りのチョコやたこ焼きを渡して彼を喜ばせたいんじゃなくて、喜んでいる彼を見て一方的に満たされて、喜んだり癒されたりしたいだけなのかもしれない。この気持ちって、ただの自己満足であって、エゴなのだろうか? 頭の中でぐるぐると考えが渦を巻いて、気がつけば、松田に向かって話しかけていた。
「バレンタインとかじゃなくてもいいんだけど、プレゼントとかってさ」
「うん?」
松田が口いっぱいにたこ焼きを頬張りながら、私に目をむける。
「私は、もらうよりもあげる方が、もらってる感覚があるかも」
「……なんそれ?」
「ううん、伝わらないなら、いい」
私もたこ焼きを一つもらって、そのまま頬張る。この店のものは小さい頃から何度も食べたはずなのに、夜風で少し冷えたたこ焼きはあまりに美味しくて、頬が綻んだ。
「美味しいね」
まだ、告白もできていないし、チョコの包装紙の中に入れていたラブレターも松田に渡せていない。けれど、今夜はこのまま、ゆっくりと時間が溶けてしまえばいいと思った。
作者プロフィール
カツセマサヒコ
小説家
1986年東京生まれ。2014年よりライターとして活動を開始。2020年『明け方の若者たち』(幻冬舎)で小説家デビュー。同作は累計14万部を超える話題作となり、翌年に映画化。2作目の『夜行秘密』(双葉社)も、ロックバンド indigo la Endとのコラボレーション小説として大きな反響を呼んだ。他の活動に、雑誌連載やラジオ『NIGHT DIVER』(TOKYO FM 毎週木曜28:00~)のパーソナリティなどがある。
GIFTFULで「選び直せる」バレンタインギフトを贈りませんか?
GIFTFULは贈り手がギフトを1つ選んで贈り、受け取り手はそのまま受け取る、あるいは同価格以下のギフト候補から選び直しをすることができる新しいギフトサービスです。
「相手の好みがわからなくて悩む…」
「でもありきたりなものを贈るのもちょっとな…」
などギフト選びにお悩みの際も、GIFTFULなら気軽に贈ることができます。
Minimalの生ガトーショコラや新食感カヌレなど、バレンタインにぴったりのギフトを掲載中。
もしチョコやスイーツが苦手な人でも、GIFTFULなら他のギフトに選び直しもできちゃいます!
友だちやパートナー、家族、職場の方へのバレンタインギフトだけでなく、自分へのご褒美、推し活など、どのようなシーンでもご利用いただけます。
今年のバレンタインは「選び直せる」という思いやりの選択肢も添えて、ギフトを贈りませんか?
▶ 人気のバレンタインギフトを見てみる
LINE公式アカウントをお友だち追加するとギフトにまつわる心あたたまるストーリーを受け取れます。
選び直せるギフト
贈り手が1つ選んで贈り、
受け取り手は選び直しもできる
新しいギフトサービスです。
